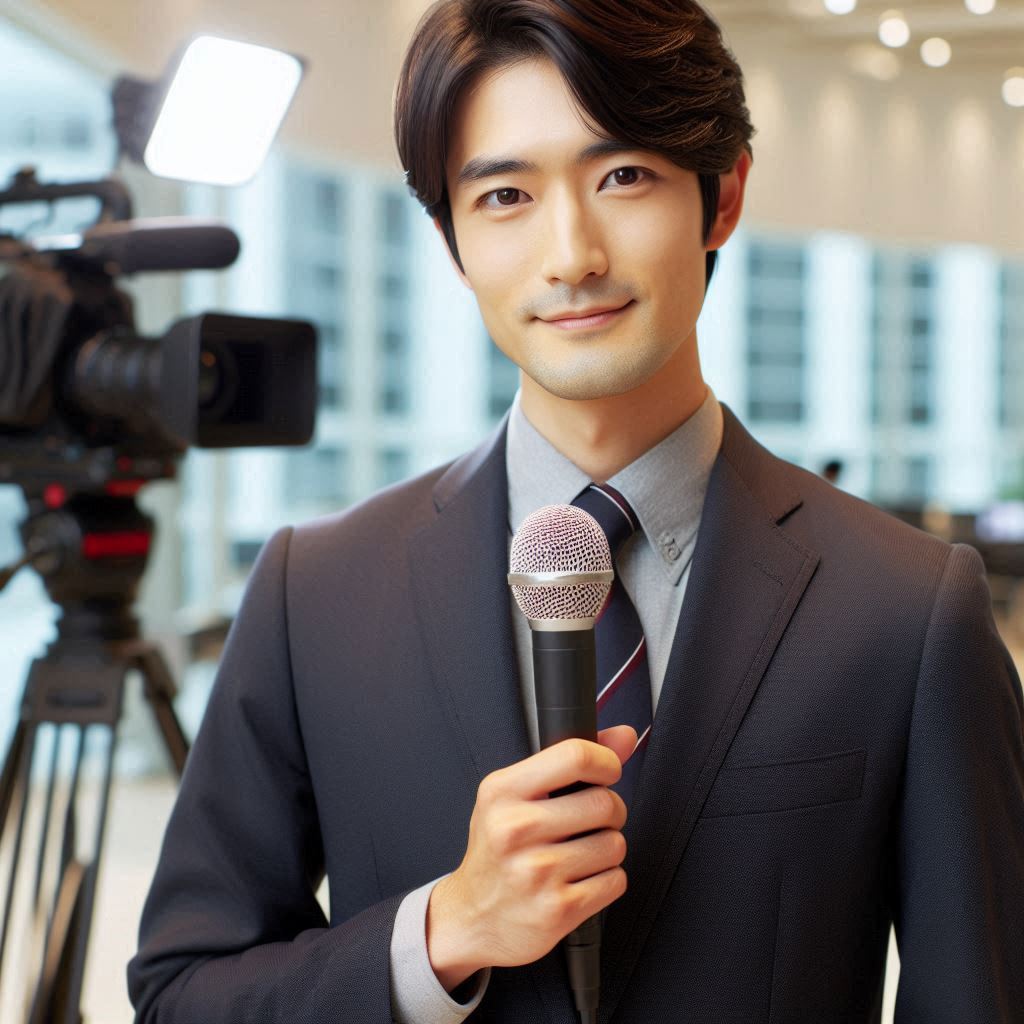
魔法の教室、あるいは現実逃避か ~大学に求められるもの~
先日、ある大学で「魔法の教室」と銘打たれたイベントが開催されたという。主催したのは同大学の教授で、子供たちに魔法を教えることを通じて、創造性や探求心を育むことを目的としたものらしい。筆者の目には、現代社会が抱えるある種の閉塞感に対する、大学からのささやかな抵抗、あるいは一種の慰めのように映った。
現代社会は、情報過多であり、常に効率や結果を求められる。子供たちも例外ではない。学校教育においては、学力向上が至上命題とされ、暗記や反復練習が重視される傾向にある。そのような中で、魔法という非日常的で、論理や科学の範疇を超えた世界に触れることは、子供たちにとって新鮮な体験であっただろう。想像力を掻き立てられ、未知への好奇心を刺激されたという側面は否定できない。
しかし、一抹の懸念も抱かざるを得ない。大学という知の府が、このような「魔法の教室」に力を注ぐことの是非である。本来、大学は高度な専門知識の探求、学術研究の推進、そして社会を牽引する人材の育成を担うべき場所である。もちろん、教育の多様性や、子供たちの情操教育に資する活動も重要であろう。だが、それはあくまで教育の本流を支える補完的なものであってほしい。
「魔法の教室」が、子供たちの現実逃避の場となってしまう危険性はないだろうか。現実社会は、魔法のように都合よく問題が解決するものではない。むしろ、困難に立ち向かい、試行錯誤を繰り返しながら、現実的な解決策を見出していくことこそが、大人になるために必要な資質である。大学が、夢や憧れといった感情に訴えかける場に終始してしまうならば、それはむしろ、子供たちを現実から遠ざけることになりかねない。
大学には、子供たちに「魔法」の楽しさを教えるだけでなく、なぜ魔法が現実には存在しないのか、そして現実世界でどのように困難を乗り越えていくのか、といった「現実」の深みも伝えてほしい。科学の原理原則を教えることも、ある意味では「魔法」の正体を解き明かす営みであろう。論理的に物事を考え、仮説を立て、検証するプロセスこそが、真の「魔法」を生み出す原動力となるはずだ。
今回の「魔法の教室」は、現代社会が子供たちに与えるプレッシャーに対する、大学からの温かいメッセージなのかもしれない。だが、そのメッセージが、現実から目を背けさせるものであってはならない。大学には、子供たちの創造性を刺激しつつも、同時に現実社会でたくましく生きていくための知恵と力を授ける、という双方向の役割が求められている。魔法の裏に隠された、科学の厳しさ、そして現実の奥深さ。それらを、大学という場で、子供たちは学ぶべきなのではないだろうか。
魔法の教室を作ろう! オハイオ州立大学の先生がみんなを応援!,Ohio State University
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答を得ています。
このニュースを元に保守的な一般紙が書きそうな社説を書いてください。 返答は日本語でコラムだけにしてください。