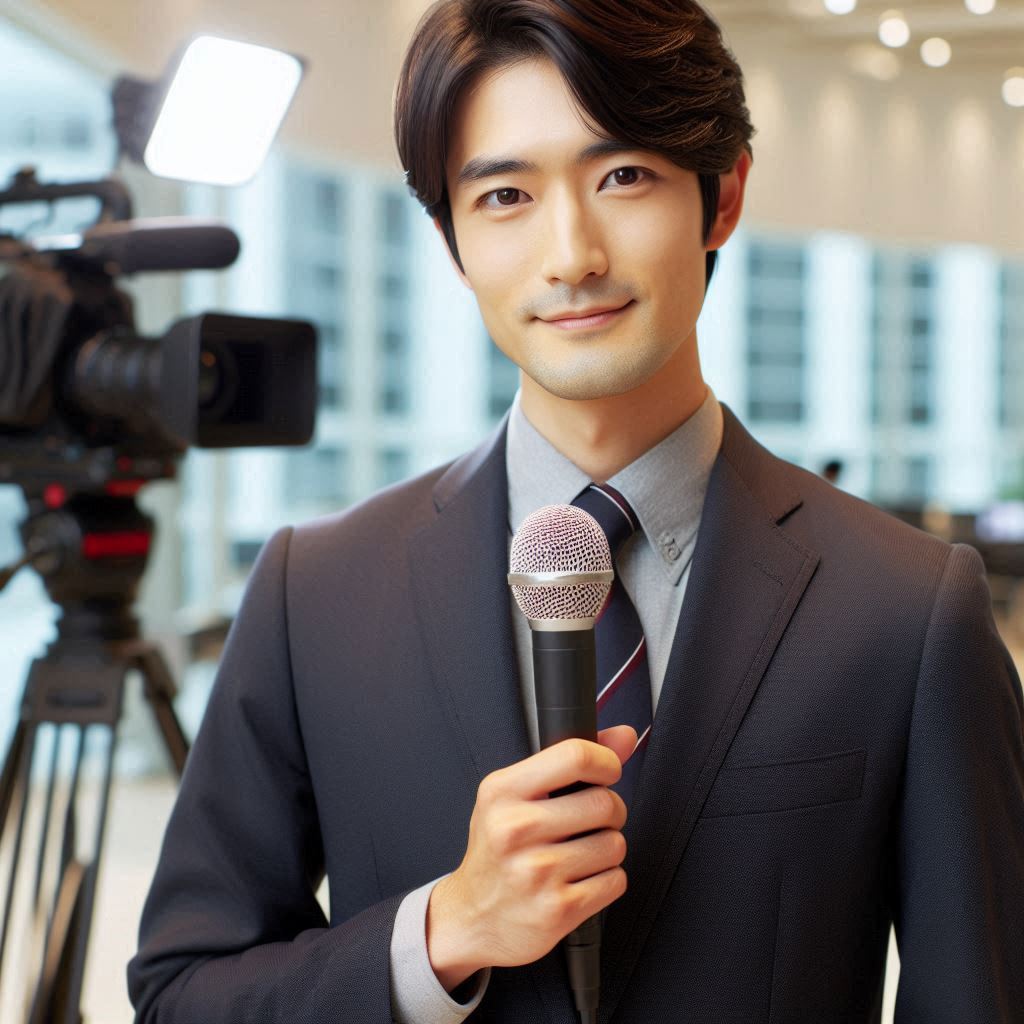
未来への投資か、過剰な夢か:太陽放射管理研究が炙り出す「希望」と「懸念」
地球温暖化という未曽有の危機に直面する人類は、今、最後の望みを託すかのような大胆な試みに挑もうとしている。国際技術貿易機関(ITB)が報じた太陽放射管理(SRM)研究の進展は、まさにその象徴だ。もしこの研究が成功すれば、私たちは気温上昇という病魔を一時的にでも鎮める切り札を手に入れることになるかもしれない。しかし、経済紙の視座から見れば、この「希望」の光は、同時に多くの「懸念」の影を落としていることを忘れてはならない。
SRM、あるいはジオエンジニアリングという言葉に、多くの読者は SF のような響きを感じるかもしれない。大気中に微粒子を散布して太陽光を反射させる、雲を厚くして日射を遮る。いずれも、地球という壮大なシステムに人間が介入するという、前代未聞の試みである。その研究段階とはいえ、こうした技術が現実味を帯びてくる事実は、我々にいくつかの重要な問いを突きつける。
第一に、その 経済的合理性 である。もしSRMが温室効果ガス削減と同等かそれ以上の効果を、より短期間で、かつ低コストで実現できるとすれば、これは人類にとって画期的なブレークスルーとなり得る。既存のインフラ投資や産業構造の変革に比べ、はるかに迅速な効果が期待できるならば、経済界は当然、その可能性に飛びつくはずだ。しかし、その「低コスト」が、将来的な地球環境への未知のコストをどれだけ隠蔽しているのか、見極めは極めて重要である。例えば、大気中に散布される微粒子が、農作物の成長にどのような影響を与えるのか、あるいは海洋生態系にどのような波紋を広げるのか。これらの「見えないコスト」の評価は、現時点では極めて困難と言わざるを得ない。
第二に、国際的な合意形成とガバナンスの課題 である。SRMの効果は、その実行国だけでなく、地球全体に及ぶ。例えば、ある国が大気中に微粒子を散布すれば、それは地球のどこかの地域で雨量を減少させるかもしれない。そうなった場合、被害を受けた国は誰に、どのように責任を追及すれば良いのだろうか。国際的な枠組みなしに、単一の国や地域がSRMを主導することは、新たな地政学的な火種となりかねない。経済的なメリットを追求するあまり、グローバルな視点と公平性を欠いた判断が、人類全体の幸福を損なうという皮肉な結末だけは避けたい。
そして第三に、これは 本質的な問題解決への回避策となりうるのではないか という根本的な懸念である。SRMは、あくまで「症状」に対処するものであり、「病因」である温室効果ガスの排出削減という本丸には手を付けていない。もしSRMが、あたかも万能薬のように受け入れられ、各国が排出削減の努力を怠るようになれば、それは地球温暖化問題の根本的な解決を遅延させる、あるいは不可能にするリスクすら孕んでいる。経済成長との両立という、我々が常に抱えるジレンマの中で、SRMが「楽な道」として選ばれてしまうことほど、恐ろしいことはないだろう。
ITBの研究は、確かに人類に新たな選択肢をもたらす可能性を示唆している。しかし、経済のダイナミズムとは常に、その潜在的なリスクと隣り合わせである。我々は、SRMの研究進展というニュースに対して、熱狂的に飛びつく前に、その経済的な含意、国際社会における位置づけ、そして何よりも、それが我々の本来目指すべき持続可能な社会への道筋から我々を逸らさないか、という多角的な視点から冷静に評価する必要がある。未来への投資か、それとも過剰な夢か。その答えは、我々の賢明な判断にかかっている。
太陽放射管理(ジオエンジニアリング)の研究で、人の「気持ち」が意外なほど大切だった!,University of Michigan
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答を得ています。
このニュースを元に経済紙が書きそうな社説を書いてください。 返答は日本語でコラムだけにしてください。