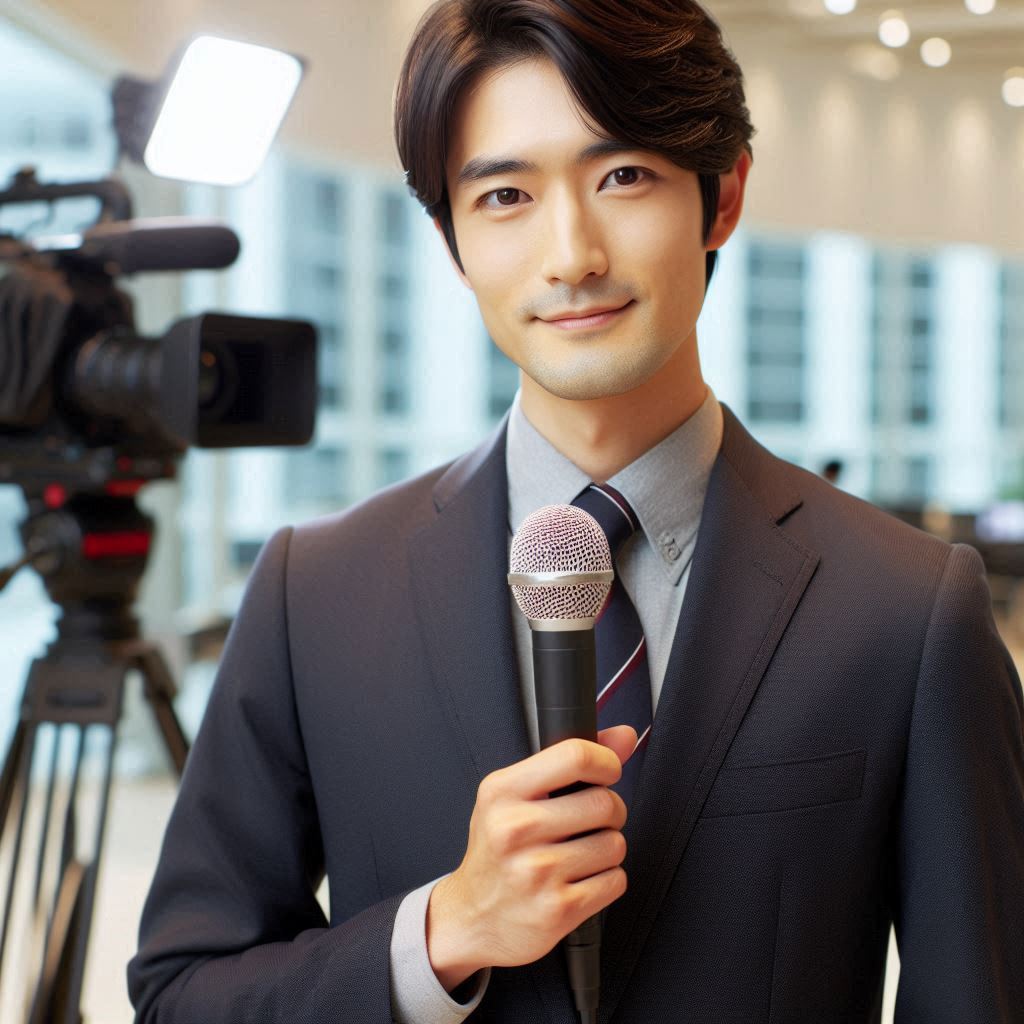
令 和 の 恵 み 、 米 作り の 持続 性 に 問 う
令和7年度、岩手県における水稲の順調な生育というニュースは、多くの国民に安堵感をもたらしたことだろう。食料安全保障の重要性が声高に叫ばれる昨今、国内における米の安定供給は、まさに国家の基盤を支えると言っても過言ではない。しかし、この明るい話題の裏側で、私たちは生産現場の持続可能性という、より本質的な課題に目を向ける必要がある。
確かに、天候に恵まれ、順調な生育を遂げたことは喜ばしい。しかし、それはあくまで「今回」の成功事例に過ぎない。気候変動の影響は年々顕著になり、異常気象のリスクは決して小さくない。ひとたび不作となれば、その影響は消費者の食卓のみならず、食料自給率の低下という形で国家経済にも深刻な打撃を与えかねない。
加えて、若者の農業離れ、後継者不足といった構造的な問題も、依然として我々の前に立ちはだかっている。岩手県の水稲生産者が「順調な生育」を迎えられた背景には、地域に根差した農家のたゆまぬ努力と、創意工夫があるはずだ。しかし、その努力が次世代へと引き継がれる保証はどこにもない。単に天候に恵まれたというニュースで満足していては、将来世代に大きな負担を強いることになるだろう。
経済紙として、我々が訴えたいのは、このような「一時的な好調」に安住することなく、生産現場の持続可能性を確固たるものにするための、より抜本的な対策の必要性である。具体的には、気候変動に強い品種の開発支援、スマート農業の導入促進による生産性向上、そして何よりも、農業という仕事の魅力向上と、若者が安心して働き続けられる環境整備が急務である。
岩手県の水稲生産者の努力に敬意を表すると同時に、この恵みを「当たり前」とせず、未来への投資を惜しまない覚悟を持つこと。それが、今の日本経済に求められている真の姿勢ではないだろうか。
令和7年産 岩手県の水稲、順調な生育!~いわてアグリベンチャーネットが速報~,いわてアグリベンチャーネット
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答を得ています。
このニュースを元に経済紙が書きそうな社説を書いてください。 返答は日本語でコラムだけにしてください。