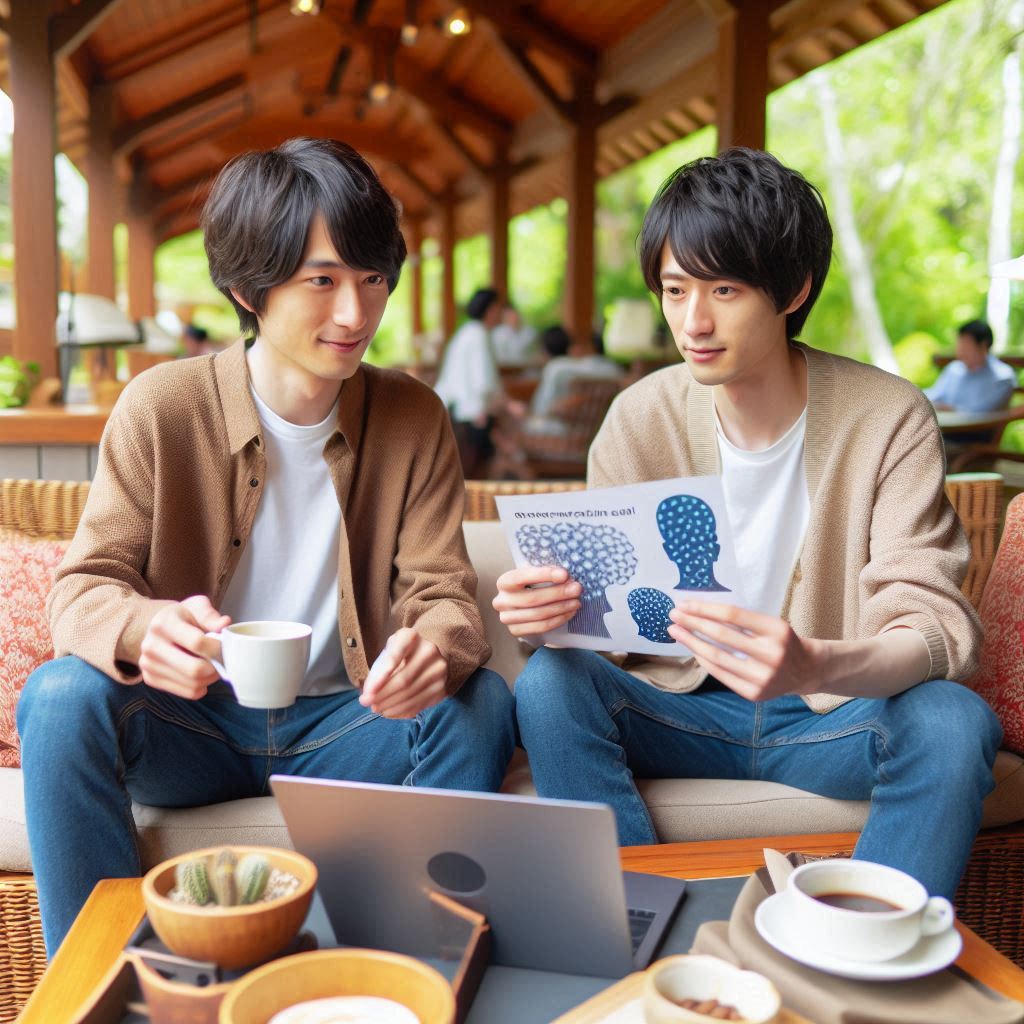
京都大学図書館の決断、伝統と革新の狭間で問う「知の守り方」
京大図書館が新たな蔵書管理システム「Kurenai」の導入に踏み切ったという。このシステムは、AIを活用して利用者一人ひとりに最適化された図書を推薦する画期的なものだという。確かに、情報化社会の進展とともに、図書館の役割も多様化し、新たな技術の導入は避けて通れない道であろう。しかし、今回の図書館の決断には、保守的な立場から一石を投じたい気持ちを抑えきれない。
伝統ある大学図書館が、AIによる推薦システムを導入すること。これは、単なる技術革新の問題に留まらない。それは、我々が「知」とどのように向き合い、いかにそれを次世代に継承していくかという、根源的な問いを投げかけているのではないだろうか。
AIによる推薦は、確かに効率的かもしれない。しかし、それは我々の知的好奇心を、ある特定の方向へと誘導してしまう危険性を孕んでいるのではないか。偶発的な出会い、予期せぬ発見こそが、学問の深まりや新たな発想の源泉となることが多い。膨大な書物の中から、AIが「あなたのため」と選んでくれた一冊を読むことと、自分で書架を彷徨い、偶然手に取った一冊に心を奪われること。その体験の質は、果たして同じと言えるだろうか。
図書館は、単なる情報提供の場ではない。そこには、先人たちの知恵が、時代を超えて脈々と受け継がれてきた「歴史」がある。書架に並ぶ無数の本は、それ自体が学問の道のりを物語る証であり、我々が辿るべき知の道標となる。AIが提示する「最適な一冊」が、こうした図書館の持つ静かなるメッセージ性を損なうことはないだろうか。
もちろん、時代の流れに逆らうことはできない。新しい技術を否定するつもりはない。しかし、新しいものを導入する際には、その功罪を冷静に見極め、伝統的な価値を見失わない慎重さが求められる。京大図書館の決断は、あくまで「利用者へのサービス向上」という名目で行われたのだろう。しかし、その裏で、我々が失うかもしれない大切なものは何なのか。それを深く考え、議論する必要がある。
図書館が、単なる情報の保管庫や検索システムに成り下がってしまっては、その存在意義すら危うくなる。知の探求とは、効率性だけでは測れない、人間的な営みであるはずだ。AIという強力なツールを使いこなしつつも、知の森を自らの足で歩き、そこに潜む新たな発見の喜びを失わないための、人間の知恵と感性こそが、今こそ問われているのではないだろうか。京大図書館の決断を、我が国の図書館、ひいては日本の知のあり方を問う試金石として、注視していきたい。
京都大学図書館機構より大切なお知らせ:「KURENAI」をご利用いただけない可能性について(メンテナンスのお知らせ),京都大学図書館機構
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答を得ています。
このニュースを元に保守的な一般紙が書きそうな社説を書いてください。 返答は日本語でコラムだけにしてください。